童具のこだわり
童具ってなに?
童具、この言葉はわたしの造語です。
子どもの遊びや学びのためにつくられた用品用具を、おもちゃ、玩具、遊具、そして、教具、教育玩具、知育玩具と呼んでいます。遊びと学びの区別をするために二つの意味を持つ言葉がつくられています。
しかし、この分け方には矛盾があります。例えば子どもは積木遊びの中で、左右の高さを同じにするためにはどうすればよいか、もっと高く積み上げるにはどうすればよいのか、常に大きさやバランスに注意して、いつの間にか数量や形態に対する認識を深めています。これは明らかに学びを深める活動でもあります。
ある数学者はこうした遊びのことを原数学活動と言っています。遊と学を区別することはできません。
童具という言葉をつくらざるを得なかった理由です。
童具は遊びながら学びを深め広げるツールです。
童謡、童話、童具、どれも子どもの精神を育む大切な文化財だと思っています。
和久洋三
面取りは最小限に
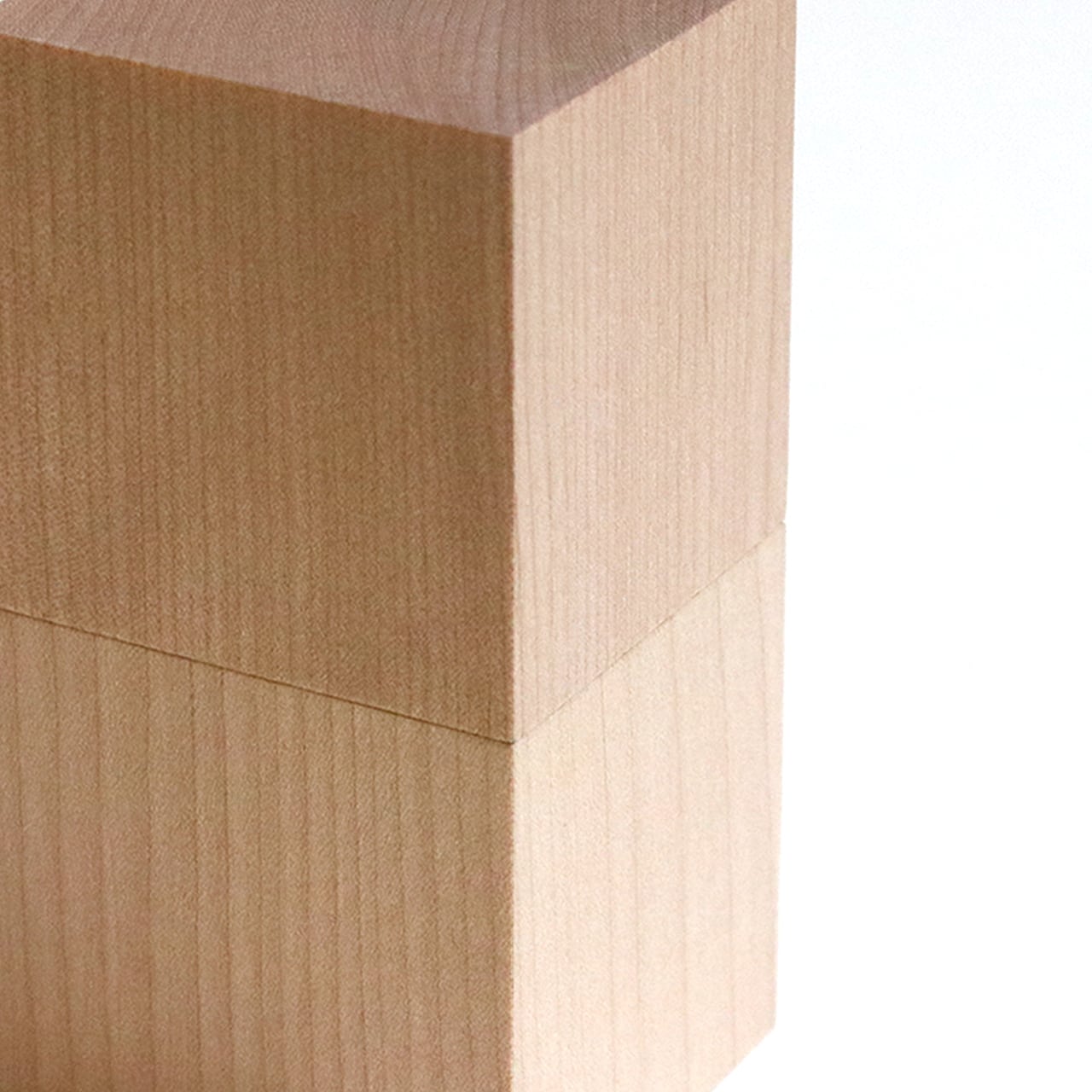
積木の角には、“糸面取り”というごくわずかな面取りを施しています。
ふたつの積木を合わせた時のつなぎ目が目立たなくなり、積木がピタッとひとつにつながる感覚、“一致への希求”が子どもを満足させます。
白木の魅力
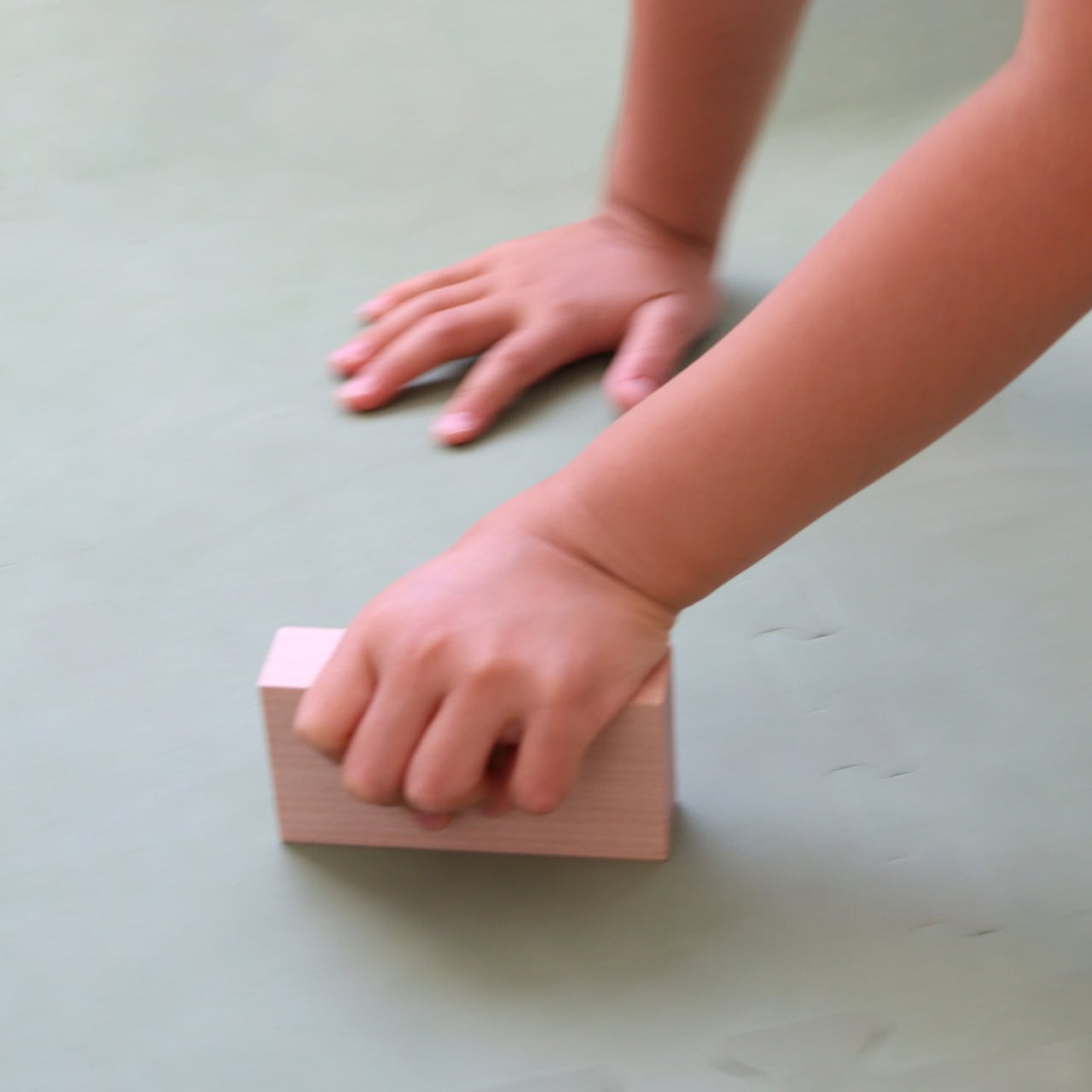
消防車をイメージすれば赤色になり、救急車をイメージすれば白色になる…。
白木は子どものイメージの中で何色にでも変化します。
基尺のこだわり

60mm、45mm、30mm基尺の童具は最大公約数15mm。
どの童具とも一緒に遊べます。
“木”という素材を使うこと
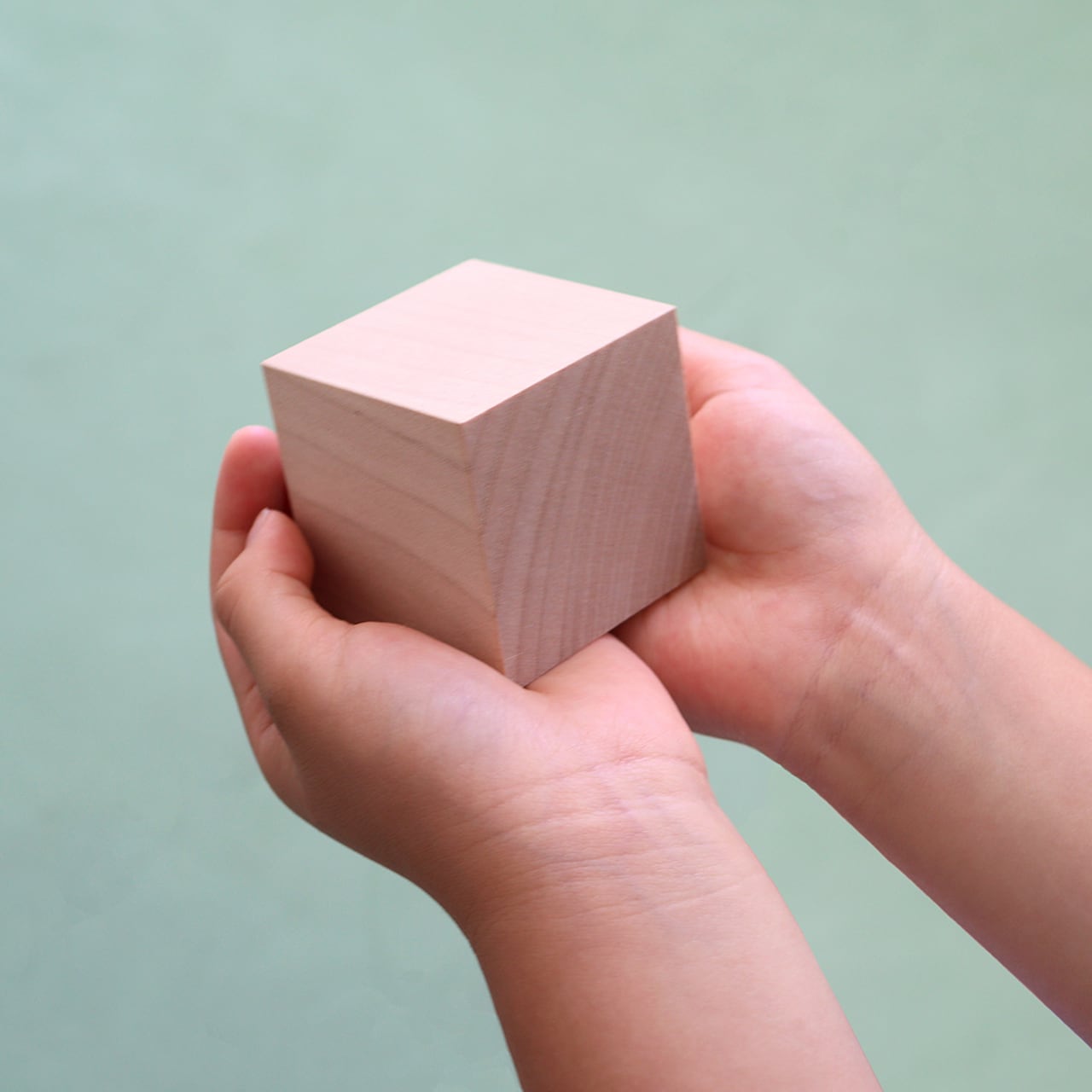
汗や涙、子どもと童具との歴史が染み込んで、絆(関係性)が深まっていきます。
100年遊びこめて、遊ぶほど艶光りしてくる素材です。
童具のことをもっと知りたい方はこちら

